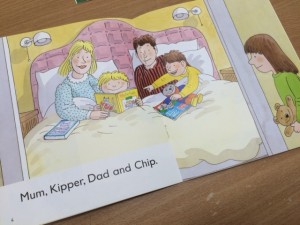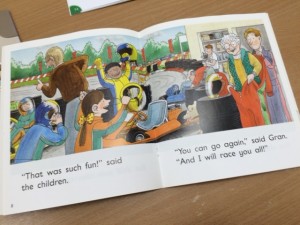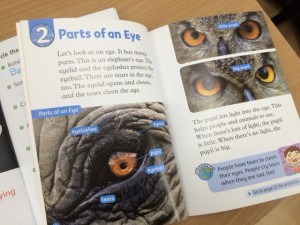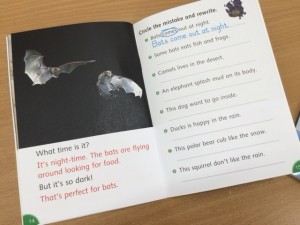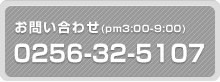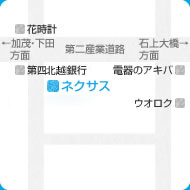こんばんは、山村です。
今回は高校数学のノートをどうまとめているのかをお見せします。
![IMG_2152[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21521-300x300.jpg)
個人的におすすめしたいのが、コーネルメソッドのノート(方眼)です。
コーネルメソッドのノートは基本的に3つの部分に分かれており、
①ノート部分
②キーワード部分
③まとめ部分
という構成になっています。
![IMG_2144[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21441-300x300.jpg)
ノート部分には普通に問題を解きます。
左側には公式を書きます。ここでポイントなのは、その章で何度も出てくる公式を出てくる度に書く、ということです。
ちなみに私がノートをとっている目的はちょっとひっかかる問題があったときに自分の解法をすぐに思い出したいからです。
そういったときに、その章にとっては当たり前でもしばらくすると忘れてしまうような、細かい公式を一々参考書を引き直す手間はもったいないわけです。
「参考書の知識と解法が一体型のノート」にするためには公式は必須なのです。
![IMG_2140[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21401-300x300.jpg)
うっかり忘れそうな超初級のことも書いておきます。
「あ~そうだったそうだった」ということを瞬時に思い出すには必要なんです。
![IMG_2138[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21381-300x300.jpg)
公式をあまり用いない問題では、解き方の手順を書くようにしています。
理想としては、この手順の部分だけを見ても問題が解けるくらいが良いです。
![IMG_2142[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21421-300x300.jpg)
グラフのパターン分けに用いることもあります。
高校数学は解答のバリエーションが多い場合がありますので、ノート部分には計算式・左側でグラフを書いて補います。
![IMG_2136[2]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21362-300x300.jpg)
ちなみにうっかり解答の手順で間違えてしまったところは消さずに残しておきます。
2度ひっかかってしまったら、それはかなり要注意の問題ということになります。
![IMG_2150[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21501-300x300.jpg)
ちなみにペンは3色ペンがおすすめです。色分けのときにいちいちペンを持ち替えるのは面倒ですので。
基本的には黒は普通の計算式・赤は公式または解法の手順・青は見直したときにハッと思い出せるような自分用のワンポイントアドバイスを書くときに使っています。
③まとめ部分についてはあまり使うことがありませんが、時間があるときは問題文を写すなどしています。問題集とにらめっこをせずに済むからです。
ということで今回は高校数学向けのノートの作り方でした。参考にできる部分があれば幸いです。
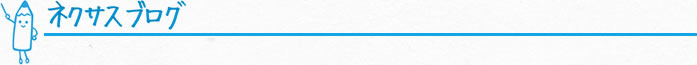
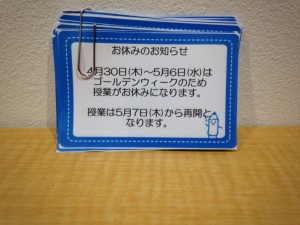
![IMG_2152[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21521-300x300.jpg)
![IMG_2144[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21441-300x300.jpg)
![IMG_2140[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21401-300x300.jpg)
![IMG_2138[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21381-300x300.jpg)
![IMG_2142[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21421-300x300.jpg)
![IMG_2136[2]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21362-300x300.jpg)
![IMG_2150[1]](http://tutorial-nexus.com/wp-content/uploads/2015/04/IMG_21501-300x300.jpg)