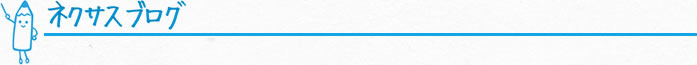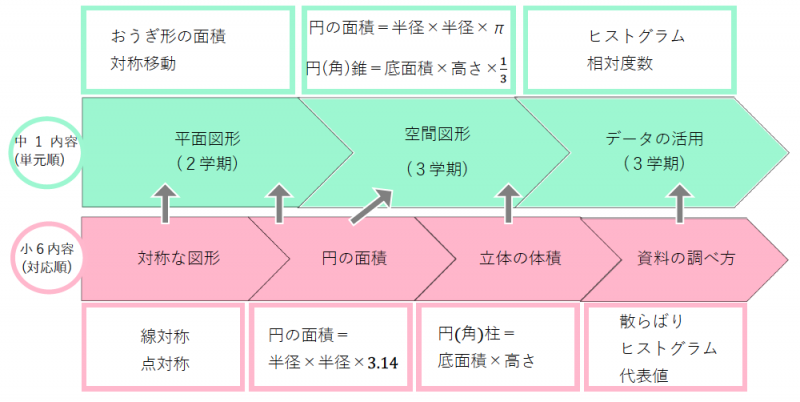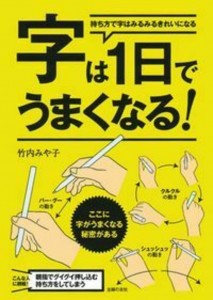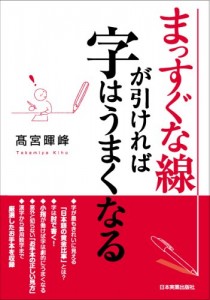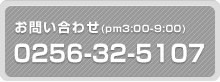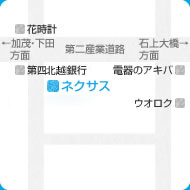一般動詞とbe動詞の区別はついていますか?
こんにちは、ゴールデンウィーク真っ只中ですね。部活に勉強に大忙しの時期です。
さて今回は、中1英語でつまづきやすい2つの動詞の使い分けについて記事を書こうと思います。
まずは役割の話から。動詞とは動作や状態を表す品詞です。基本的な使い方としては主語の次にくる単語、といった感じでしょうか。
英語の動詞には2種類あります。be動詞と一般動詞です。
be動詞は数が少なく、基本の現在形は3つだけ・・・am / is / are です。原形はbe、過去形はwas / were となります。これだけです。
一方一般動詞は中1の最初に習うものだけでもたくさんあります。 play / like / do / read / write・・・ などですね。
2つの動詞は平叙文の場合は ほとんど区別がないように見えます。
I am a teacher.
I like dogs.
平叙文では ➀主語の次に来る(例外もあります) ➁時制によって現在形、過去形など変化する という2つのポイントが重要です。
ただ、疑問文と否定文では違った書き方になります。
まずは疑問文からです。
Are you a teacher?
be動詞の文はシンプルです。➀主語とbe動詞を入れ替える ➁最後に?をつける
Do you like dogs?
それに対して一般動詞はどうでしょう。 ➀Do ( Does / Did )という助動詞と呼ばれるものを先頭に差し込む ➁一般動詞は原形に戻す ➂最後に?をつける
be動詞に比べて作業が多いですね。
次は否定文です。これも一般動詞のほうが作業が多くなります。
I am not a teacher.
➀be動詞の後ろにnotを入れる。 be動詞の文の否定文はこれだけです。
I do not like dogs.
➀do ( does / did )という助動詞と呼ばれるものを一般動詞の前に差し込む ➁さらにnotをその後ろに入れる ➂一般動詞は原形に戻す
don’t など、➀➁をくっつけることもできます。ただ、don’t だけを覚えていると I am don’t a teacher. のようなミスをしてしまいます。
don’t = do not としっかり覚えておく必要がありますね。
中1生の第1回の定期テストではこの使い分けがとても大切になります。三条市内の中学校は3年前から英語の教科書がNew Crownに変更され、習う順番がこれまでよりも複雑になっています。レッスン1からつまづきやすくなっていますので、これらの使い分けをしっかりとマスターしてテスト本番まで練習を重ねていきましょう。